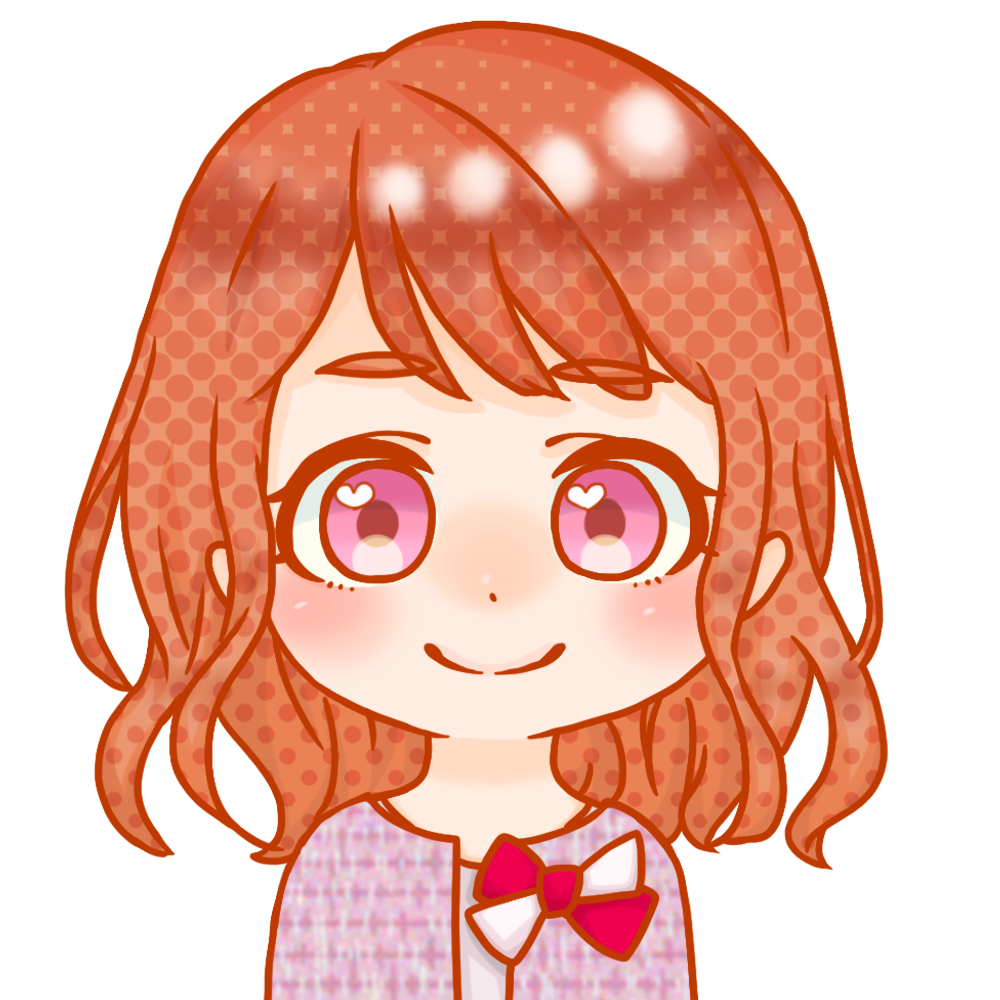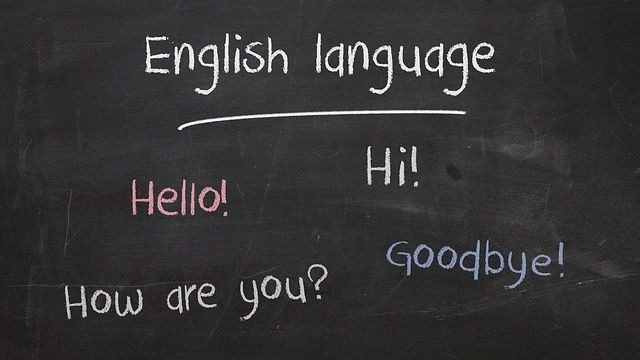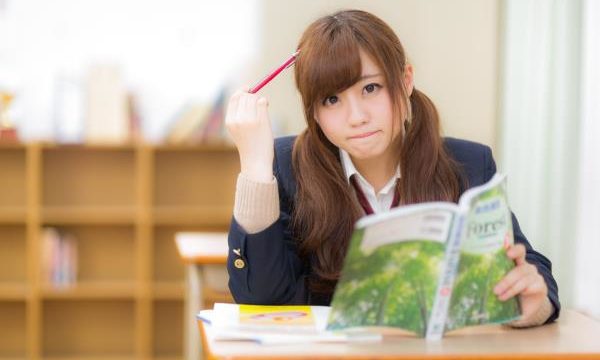受験生にとって文理問わず、英語は必須科目ですよね。
受験において英語が出来るということは、大きな得点元になります。
それはつまり、
得点に関して自信と安心感がつきますし、
第一志望の大学合格に大きく近づけるということです。
実際に、センター試験では配点が200点となっています。
つまり、これは国語(200点)と同じ程、大きく配点を占めていると言えるのです。
だからこそ、英語の勉強は受験生にとっては誰もが必要な科目と言えます。
実は、2020年度から英語の試験形式が変わると言われています。
試験の形式が変わることは大きな不安になりますよね。
「これからはどう勉強すれば良いのかな?」
「今までの勉強法で良いのだろうか?」
このように思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そうですね……私たちの年から大学共通テストに変わるので………対策が不安なんですよね……
— 大納言あずき (@tRXEiUNIrCfcasX) January 27, 2019
実際に不安の声も聞こえてきますね。
今回は美月の高校の先生に話を聞きながら、
皆さんに是非知ってもらいたい英語の試験形式と、使用できる民間資格、
そして、新たに必要になる英語の勉強法についてお伝えしたいと思います。
2020年度から新制度!全国共通テストが始まる
2020年度、つまり2021年に入学する年から、
いわゆるセンター試験は見直され、『大学共通テスト』というものが始まります。
それに伴って、試験の形式にも変化が生じます。
特に英語はその変化が大きい教科だと言えるでしょう。
4技能の能力が問われる
今後は読む・聞く・書く・話すといった英語の4技能が問われていきます。
従来のセンター試験であれば読む・聞く、つまり、リーディングとリスニングの2技能だけを問われていました。
しかし、今後は書く・話すといった、ライティングとスピーキングが加わります。
そのため、英語の試験対策は今まで以上に負担が大きくなると予想できます。
2024年度までは民間資格、検定との併用
大学共通テストで4技能の全てを測るということは出来ません。
そのため、2024年度までは大学共通テストと民間の資格、検定と併用することになります。
また、大学共通テストなのか、民間の資格、検定なのか、あるいは併用なのかということは、各大学が利用方法を決定します。
センター試験のような共通の英語のテストは事実上無くなったと言っても良いでしょう。
大学入試で使える民間資格・検定の種類
大学入試で使える民間資格と検定の種類には、以下のようなものがあります。
・ケンブリッジ英語検定
・TOEFL iBT
・IELTS(IDP:IELTS Australia実施)
・IELTS(ブリティッシュ・カウンシル実施)
・TOEIC
・GTEC
・TEAP
・TEAP CBT
・実用英語技能検定
各検定や試験の概要については、大学入試センターに詳細が記載されています。
現時点では、資格や検定が絶対に必要になるとは限りません。
何故なら、各大学が英語入試の方式を決めるからです。
そのため、大学によっては資格や検定が必要ないところもあります。
リーディングとリスニングの勉強法【センター試験とどう違う?】
従来のセンター試験で出題されていた、リーディングとリスニングの問題も変化すると考えられています。
配点についてはまだ公表されていないものの、リーディングとリスニングの配点を同じにするよう検討しているようです。
詳しく知りたい方は、高校生新聞のこちらの記事を参考にしてみてください。
そうなると、「今までの勉強法は通用するのだろうか?」と、心配する方もいらっしゃると思います。
ここからは美月の高校の先生に話を参考に、
今後も通用するリーディングとリスニングの勉強法について聞いていきたいと思います。
【美月の高校の先生】
久しぶりだね!今日はよろしくお願いします。
大学入試のリーディング
リーディングはセンター試験の英語で一番配点を大きく占めています。
そして、大学共通テストではリスニングと変わらない配点を占めると考えられています。
美月の高校の先生はどのように、配点の大きいリーディングを勉強したのでしょうか。
【美月の高校の先生】
最初は文法と単語から勉強し始めました。私も試験の形式が変わるのは知っていました。
しかし、例え形式が変わるとしても、やはりこの2つから始めることが重要です。
【美月の高校の先生】
リーディングの勉強は大きく、文法、単語、長文読解に分けられます。順を追って話しますね。
文法の勉強
文法は英語を作る骨格と言えますが、覚えることが多いですよね。
その量を前にして、勉強を諦めてしまいたくなる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
では美月の高校の先生は一体、どうやって文法を勉強し始めたのでしょうか。
【美月の高校の先生】
まずは1冊ずつ文法書と文法問題集を買って、問題集をひたすら解いていました。
最初は知識が無いので、基礎的な問題集ですら歯が立ちませんでした。
しかし、その度に問題集の解説、そして文法書を行き来していました。
【美月の高校の先生】
最初はもちろん苦労しましたよ。
でも、文法書はこだわって選んだおかげで、図やイラストがあって分かりやすかったのです。
そのため苦労はしましたけど、理解しやすく、飽きずに勉強できました。
文法は量が多く、勉強が単調になりがちです。
しかし、その単調さに反して、文法は覚えておかなければいけないことがたくさんあります。
そのため、理解しやすい勉強法を確立しておくことがとても大事です。
【美月の高校の先生】
まず文法書は、デュアルスコープ総合英語という総合英文法書を使っていました。この本は全部カラーで、図やイラストもあるので視覚的に英語を理解できました。
問題集はNext Stageという問題集をひたすら何周も解いていました。
何周も解いて、問題を見ただけで答えが分かるところまで来たら、上のレベルの問題集を買いました。
頻出英文法・語法問題1000というものです。
美月の高校の先生のように、自分に合う参考書を見つけることは重要です。
それが今後の勉強が続くかどうかを左右するからです。
特に、文法書は文字だけのものではなく図やイラストがあるものを選びましょう。
そうすることで、視覚的にも覚えることが出来ます。
美月の高校の先生が使っていた参考書は以下の通りです。
英単語の勉強
単語も文法と同じく、量が多く、勉強が単調になりがちです。
美月の高校の先生は、どのように膨大な単語を覚えられたのでしょうか。
【美月の高校の先生】
やはり単語帳もこだわりました。
特に重視したのは音声がついているということです。
目で見るだけではなく、スキマ時間に音声を聴くということも出来ますので、今の生徒にも音声付きのものをおすすめしています。
ちなみに私は当時、友達から薦められてユメタンというものを使っていました。登下校中に聞き流して、忘れた単語があったら単語帳を開くということをしていました。
文法と同様に、単語も飽きずに覚えられる勉強法を確立しておくことが重要です。
そのため、美月の高校の先生のように、単語帳も自分に合ったものを選ぶ必要があります。
現在ではCDつきのものもあれば、インターネットから音源をダウンロードするものもあります。
美月の高校の先生が使っていたユメタンはアルクショップから購入できます。
ユメタンはレベルごとに分かれており、高校生向けのものであれば0から3まであります。
「英語が苦手で単語は特に自信が無い…。」という方は0から始められるのが嬉しいポイントです。
単語に苦手意識が無いという方に対しては、1から始めることをおすすめします。
英語の長文読解
長文読解は、今まで覚えてきた単語と英文法の総合演習と言えるでしょう。
何故なら、単語と英文法という基礎が無ければ長文は読めないからです。
【美月の高校の先生】
長文の問題集はとても良いものを知っています。
やっておきたい英語長文シリーズというものです。
私はこれをまず解き、答え合わせの際に分からない単語を調べるということをしていました。
全て解き終わり1週した後は、声に出して読むということをしていました。
これは長文を読むスピードを速くするためです。
あとはリスニング・スピーキング対策という意味もありましたね。
それはまた後でお話しします。
【美月の高校の先生】
いえ、最初の内はしていませんでした。
しかし、上のレベルのものを買って解く際は時間を測りながら解いてましたね。
美月の高校の先生の薦める『やっておきたい英語長文シリーズ』もレベルごとに分かれています。一番文字数の少ないもので300、一番多いもので1000まであります。
こちらも自分のレベルに合わせて、購入することをおすすめします。
しかし、志望大学に関わらず、300と500は解いておきたいところです。
何故なら、従来のセンター試験レベルの長文を安定して解けるようにするためです。
美月の高校の先生が使っていた『やっておきたい英語長文シリーズ』はこちらから。
【美月の高校の先生】
おすすめの勉強法としては、
300と500の前半の問題までは自分のペースで解き、
500の後半の問題からそれ以上のレベルの問題は、時間を測ることをおすすめします。
500の問題を解ける頃には、ある程度英文が読める状態です。
そのため、このタイミングで時間を意識した勉強法に切り替えるのが良いです。
ある程度慣れて練習しないと、本番で慌てちゃうよね。
本番は時間との勝負になります。
そのため、長文読解でも、限られた時間の中で問題を解く練習をしておきましょう。
リーディング勉強法まとめ
美月の高校の先生の話を参考にすると、以下のようにまとめられます。
・文法:文法書は理解しやすいものを買うこと!
文法書と問題集を行き来しながら何度も同じ問題を解くことから始めよう。
・単語:音声付きのものを買って耳からもインプットすること!
スキマ時間を上手く利用しよう。
・長文読解:文字数の少ないものから始めること!
レベルを上げるごとに時間を測ってみよう。
大学入試のリスニング
リスニングはセンター試験でも出題されていますが、多くの受験生が苦手とする分野だと思われます。
配点の面では、250点の内の50点なので、リーディングに比べて配点は小さいです。
しかし、大学共通テストではリーディングと同じ配点にするという動きもあり、今まで以上に勉強が必要になる分野です。
使った本は1冊!?リスニングの勉強法
では、美月の高校の先生はどのようにリスニングを対策していたのでしょうか。
【美月の高校の先生】
実はこれと言った対策はしていませんでした。
使った問題集も1冊だけですし、「勉強するぞ」という意識はリーディングに比べて薄かったのです。
【美月の高校の先生】
まず、使った本は大学入試センター試験英語リスニング実戦問題20回というものです。これを何周も繰り返して解いて、問題文を聴きつつ自分でも音読していました。
音読をすることは、自分の喋った英語を耳で聞くことになります。
それに英語のリズムを体得できるので、おすすめの勉強法ですよ。
英語の勉強の基本は繰り返すことです。
やはりリスニングも繰り返すことで、耳を慣らすことが出来ますし、他の問題に応用することが出来ます。
美月の高校の先生が使用していた問題集はこちらから。
【美月の高校の先生】
あとはTEDというものを聴いていました。
TEDは専門的な話が多いので、もちろん字幕付きで聴いていました。
字幕については強調したいのですが、最初は日本語、2回目以降は英語字幕で聴いてみてください。内容を理解してから、どのような英語が使われているかを知るためです。
最初は聞き流すという気持ちで良いと思います。
あとは、あまり時間の長くないスピーチを選ぶことと、自分の興味のあるものを選ぶことをおすすめします
続けている内に理解できる範囲が大きくなっていきますよ。
私たちは日本にいる内は、常に英語が聴ける環境ではありません。
そのため、意図的にどれだけ英語を聴ける環境にするか、ということが大事になります。
耳から入ってきた英語が理解できる瞬間は、とても嬉しいものです。
是非コツコツ続けて、美月の高校の先生のように、理解できる範囲を大きくしていきましょう。
TEDとは、それぞれの分野のスペシャリストがあるテーマに沿ってスピーチをします。
その多くのスピーチの動画が見れるというものです。
海外のスピーチが見れるTED
アプリもありますので、気になる方は是非ダウンロードしてみてください。
スキマ時間に聴けるのも嬉しいですね。
リスニング勉強法まとめ
美月の高校の先生がしていた、リスニングの勉強法は以下のようにまとめられます。
・問題集は1回解いたら終わりではなく繰り返すこと!
何度も聴きながら音読もしてみよう。
・本だけに頼らない耳を慣らす勉強をしよう!
TEDで自分の興味のあるスピーチを探してみよう。字幕は日本語のみに頼らず英語でも聴いてみよう。
新制度で追加!ライティングとスピーキングの勉強法
ライティングもスピーキングも今までは一部の大学でしか必要が無かったので、
一般的な勉強法はまだ確立していないですよね。
それに、リーディングに比べ、どこから手をつければ良いか分からないことが多いです。
しかし、それはみんな同じことなのです。
逆に言うならば、早めに勉強法を確立しておくことで、周りと差がつけられると言うことです。
大学入試のライティング
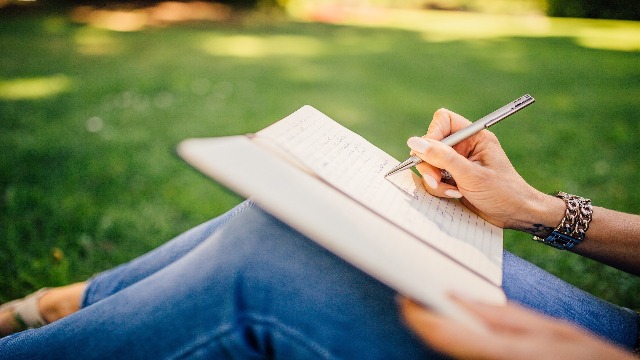
ライティングは多くの受験生が苦手とする分野です。
何故なら、授業で英語を書く機会は、読む機会より少ないからです。
基礎は文法と単語
まず、ライティングの勉強をするにあたって、一体どこから始めれば良いのでしょうか。
【美月の高校の先生】
はっきり言ってしまえば、やはり文法や単語が何より基礎の土台になります。
日本語を見て、文の組み立て方は分かるけど単語が分からなかったり、
逆に、単語は分かるけど文の組み立て方が分からないことは、とてももったいないです。
そのため、ライティングの勉強をするにあたって、
リーディングのための勉強が基礎になることは間違いありません。
ライティングと言っても、結局書くものは英語の文章です。
そのため文法知識という型と、単語という肉付けが必要になります。
日本語をより簡単な日本語に
美月の高校の先生は、具体的にどのようにライティングに取り組んでいたのでしょうか。
【美月の高校の先生】
実は、ライティングの教材は問題集1つも使っていませんでした。
なので、過去問から使えそうな例文を使っていましたね。
そして、勉強している内に気付いたのですが、ライティングとは、
・まず日本語を簡単な日本語に直す
・日本語に合う英文法をあてはめる
という作業が重要だと感じました。
ライティングと聞くと、『難しい日本語の文をそのまま訳して、難しい英語を使って書かないといけない』と考えがちですよね。
一つ例文を見てみましょう。
読書は人生をより豊かにしてくれる。
このような文があった時に、まず日本語を簡単な日本語にします。
すると、
本を読むことは人生を更に豊かにする。
この形にすると、『を~にする』は『make+O(目的語)+形容詞』という表現と結びつけることが出来ますので、動詞にmakeを使うことが出来ると予測できます。
以上から英文を組み立てると、
Reading books make life richer.
となります。
このように、実際は日本語をまず簡単にすることから始めれば、簡単な英語を使うことが出来るのです。
インターネットの力を借りる
自分だけで英作文を書いても何が正解か分かりません。
一人で勉強していると、このような状況に多く出くわしますよね。
美月の高校の先生はどう対処していたのでしょうか。
【美月の高校の先生】
その時はインターネットの力を使っていました。
HiNative
具体的には、HiNativeという言語学習質問サイトや、HelloTalkという言語交換アプリを使っていましたね。
自分で英作文を書いたとしても、英語の知識があって見てくれる人がいなければ、どこが間違っているか分からないですよね。
しかも、自分が教えてほしい時に、いつもそのような人が側にいてくれるとも限りません。
【美月の高校の先生】
私は高校の時の英語の先生が忙しそうだったので、インターネットに頼りきりでした。
現在、英語学習はネットでも盛んになってきました。そして一番のメリットは、
世界中の多くの人がそのサイトを見ているということです。
英語は世界中の人々が勉強する言語なので、1つの投稿が色々な人の目に触れやすいです。
英作文に関しても、ネイティブの目に触れやすいインターネットの力を使うことは、大きな力になります。
HiNativeはYahoo知恵袋のようなシステムで、言語に特化した質問サイトです。
特に英語は話者数と学習者数ともに多い言語なので、質問への回答が比較的早いです。
DMM英会話パイセンとHinativeパイセンには常日頃からお世話になっております。特に日本語から英語に言い直したい時に。おっすおっす。
— みくみお (@miow_cherry147) April 15, 2019
HiNativeの公式サイトはこちらから。
HiNative
HelloTalk
HelloTalkは言語交換サイトです。
自分の勉強している言語を英語に設定することで、『英語話者で日本語学習者』とマッチングすることが出来ます。
また、タイムラインで『英語話者で日本語学習者』の投稿が見れるので、
お互い教えあうことのできる友達を見つけられます。
また、HelloTalkはスピーキングでも活用できます。
最近よく語学勉強する時に便利なアプリ聞かれるのですが、自分の場合基本この3つでした!
・Hello Talkで色んな国の人とチャットして文法勉強しながら世界中に友達作る!
・TEDでリスニングの練習しながら色んな人の面白い話聞く!
・Duolingoで英語使って第2言語勉強する!
基本、一石二鳥ね! pic.twitter.com/bgcdIpzzmj
— かいと@外国人との日常を発信中 (@1203Ka) April 10, 2019
HelloTalkの公式サイトはこちらから。
HelloTalk
Hello Talk (ハロー トーク) : 言語交換 学習
HELLOTALK FOREIGN LANGUAGE EXCHANGE LEARNING TALK CHAT APP無料posted withアプリーチ
ライティング勉強法まとめ
美月の高校の先生のライティングの勉強は、このようにまとめられます。
・文法知識と英単語を固めること!
リーディングの勉強は継続して続けよう。
・ 過去問から英作文の問題だけ使うこと!
実践的な問題に触れておこう。
・ 自分なりに英作文を書いてみよう!
日本語を簡単な日本語に直すことから始めよう。
・インターネットに自分の文をアップロードし、添削してもらおう!
どこが間違っているのかを確認しつつ、ミスを少なくしていこう。
ライティングだからと言って新しい勉強ではなく、リーディングの基礎知識を活用しましょう。
大学入試のスピーキング

スピーキングもライティング同じく、どこから手を付けていいか分からない分野ですよね。
それに「難しそう」と思う人が多くいるのではないでしょうか。
加えて、英語が話せる人を見つけた上で、練習に付き合ってくれる人を探すのだけでも一苦労です。
ネイティブとスピーキング練習
美月の高校の先生もそういう状況だったので、やはりスピーキングもインターネットの力を借りていました。
【美月の高校の先生】
私も最初から話せたわけではありません。
会話に関してはHelloTalkというアプリでチャットをしていました。
チャットは、先ほど話したライティング技術が活かせるので、問題はありませんでした。
しかし、音声会話になった途端、「Hello.」や、「I am a high school student.」くらいしか話せなくなってしまいました。
ただ、数をこなしていく内にどういう流れで会話が進むか分かるようになってきたんです。
例えば、「今日一日どう過ごしていたか』とか『何で英語を勉強しているの?」とか、あとは「日本に行きたいけど、どの場所がおすすめか?」といったものですね。
事前に会話の内容が予測できれば、
どういう単語やフレーズを使えば良いか分かりますよね。
また、その英文を別の人と会話している時に使うことも出来ます。
【美月の高校の先生】
あと、どうしても聞き取れない時は、文字で書いてほしいということを伝えていましたね。
文字と相手の言っていることを一致させるようにしていました。
英語でのやり取りは、まさに英語の4技能がフルに問われます。
初めは、「分からないことだらけで不安・・・。」という方もいると思います。
しかし、HelloTalkのようなアプリでは言語学習をしている人たちが集まります。
相手が出来ないと言うことは、みんな分かっているのです。
出来なくても相手に質問をすれば良いですし、
「正しくなくても伝わればそれで十分」という気持ちでいると、どんどん話すことが出来ます。それに、話せば話すほど上手に話せるようになります。
最初の一歩は勇気がいると思いますが、スピーキング上達のために、一歩だけでも踏み出してみましょう。
オンラインでできるDMM英会話
![]() なら、
なら、
世界中の講師の先生と話せるお気軽プランと、
イギリスやアメリカの講師の先生など『ネイティブ』の人と話せるプランがあります。
まずは無料体験から、気軽にスピーキングの練習をDMM英会話
![]() でしてみましょう。
でしてみましょう。
スカイプがなくても、大丈夫ですよ。
英語を話せる環境を整える
しかし、これでは英会話は出来ますが、果たしてスピーキング試験の対策になるのでしょうか。
【美月の高校の先生】
むしろ、最初から試験対策を意識してしまうと、
本番になった時に緊張で英文が出てこないのではないかと思っていました。
そのため、普段から英語を喋っていい環境、間違っても話せる環境づくりを整えることから始めました。結果、のちに「やっておいて良かったな」と思うことがよくあります。
民間資格、検定のスピーキングテストはあるテーマについて英語で話したり、
あるテーマについて英語で質問されたり、形式は様々です。
しかし、どの試験にも共通するのが、『はっきりと明確な英語で話すこと』です。
そのため、本番で声が小さくなってしまったり、緊張で英語が出てこないというのは大きなマイナスポイントになってしまいます。
だからこそ、普段から口慣らしが出来る環境にいることでスコアアップに近づけます。
普段使う教材の音読をする
【美月の高校の先生】
あとは普段から、自分の使った問題集の問題を音読することですね。
これは英語を読む上でのリズムや、文の構造を身につけるという意味で役に立ちました。
音読を続けていく内に、英語の意味ごとの区切りを自力で見つけられるようになってきたのです。結果、英語の長文を読むスピードが上がりました。
会話だけでは無く、普段の練習もスピーキング能力アップに役立ちます。
スピーキングを練習することで得られるメリットと言えば、
・英語を語順のまま理解できる
・長文の読むスピードが速くなる
・英語の音をアウトプットすることでリスニング能力も上がる
以上のようなものが挙げられます。
こう聞くとやらない手はないですよね。
リスニング、リーディング能力もアップするのですから、早めに始めて損はありません。
まとめ
4技能とはそれぞれが分かれた能力では無く、お互いの総合能力です。
そのため、ライティングとスピーキングの対策をするからと言って、
英文法や単語の勉強をしなくなるというのは、本末転倒と言えるかもしれません。
【美月の高校の先生】
「こうすれば、英語力が上がる!」という、小技や裏技では限界が来ます。
リーディングとリスニングが『英語のインプット能力』を問われるのに対し、ライティングとスピーキングは『英語のアウトプット能力』が問われます。
これはつまり、基礎である『英語のインプット能力』が固まっていなければ、出来ないことです。
試験のために、新たに必要になるライティングとスピーキングですが、
逆を言えば基礎を固められれば怖いものは無いということです。
では、今までの勉強法をまとめて見てみましょう。
・リーディング:単語と文法をまずは固めよう!
基礎が固まったらレベル別に新しい単語や長文の問題集にも挑戦しよう。
・リスニング:教材の復習と音読を忘れないようにしよう!
スキマ時間にTEDを聞いて新たな知識と英単語を一石二鳥で勉強しよう。
・ライティング:基礎のリーディングの勉強を怠らないようにしよう!
添削はインターネットでネイティブの力を借りよう。
・スピーキング:便利なアプリでネイティブと英語の練習をしよう!
普段使う教材の音読と合わせて、英語を語順のまま理解できるようになろう。
受験英語の勉強法に自信が無いという方は、是非参考にしてくださいね。
英語の勉強は、コツコツと積み重ね、繰り返した先にゴールがあります。
今までの勉強法に少し工夫を加えれば、あとは積み重ねの大きさが物を言います。
【美月の高校の先生】
どういたしまして。最後に、私が勉強していた際に大事にしていた格言があります。それを送りたいと思います。
Rome was not built in a day.(ローマは一日にして成らず)
byミゲル・デ・セルバンテス
一見、受験の壁は厚く、そして高く見えます。
しかし、美月の高校の先生のように、使えるものは工夫して使いましょう。
そして、受験という大きな壁を乗り越えましょう!